
猫の動き方がフラフラと緩慢になり、時々よろめいて倒れたりすることがあります。普段は簡単に登れるはずの高さにも登れなくなり、ずり落ちてしまうようなことも見られるかもしれません。また、歩こうとしても、足の動きが変な場合には、他の原因が考えられます。今回は猫の歩き方がフラフラしている場合に考えられる症状や原因、対処法について獣医循環器認定医の佐藤が解説します。
この記事を執筆している専門家
佐藤貴紀獣医師
獣医循環器学会認定医・PETOKOTO取締役獣医師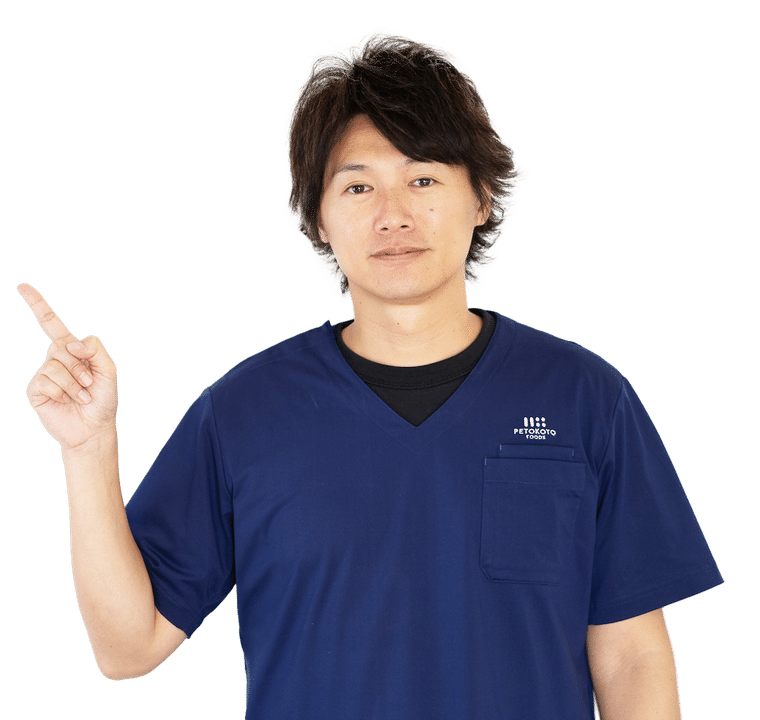
獣医師(東京都獣医師会理事・南麻布動物病院・VETICAL動物病院)。獣医循環器学会認定医。株式会社PETOKOTO取締役CVO(Chief veterinary officer)兼 獣医師。麻布大学獣医学部卒業後、2007年dogdays東京ミッドタウンクリニック副院長に就任。2008年FORPETS 代表取締役 兼 白金高輪動物病院院長に就任。2010年獣医循環器学会認定医取得。2011年中央アニマルクリニックを附属病院として設立し、総院長に就任。2017年JVCCに参画し、取締役に就任。子会社JVCC動物病院グループ株式会社代表取締役を兼任。2019年WOLVES Hand 取締役 兼 目黒アニマルメディカルセンター/MAMeC院長に就任。「一生のかかりつけの医師」を推奨するとともに、専門分野治療、予防医療に力をいれている。
猫がよろけたりふらつく場合に考えられる原因と病気

猫の歩き方がフラフラしてよろめいたり倒れる
原因としては、頭蓋内を含めた神経的な異常や重度の貧血などが考えられます。猫の場合はウイルス感染によるものが多く脳炎、髄膜炎などが見られます。心臓病、肝臓病、腎臓病などによってもこのような症状を示すこともあります。また、外に出る猫の場合は、交通事故などによる脊髄損傷も注意しなくてはなりません。
猫が急に後ろ足に力が入らなくなり、全く歩けない
この場合には、交通事故や大動脈血栓塞栓症(そくせんしょう)、そして椎間板ヘルニアという病気が考えられます。早急な対応が必要ですので、すぐ病院へ行きましょう。猫が徐々に後ろ足に力が入らなくなり、よろよろとはしていても歩ける
この場合には、脳の疾患や神経に発生した腫瘍、そして関節炎といった可能性が考えられます。また、後ろ足に限らないことが多いですが、腎不全や肝不全、糖尿病そして甲状腺機能亢進症といった内臓の疾患が原因の可能性も考えられます。猫がふらつく場合の応急処置・予防ケア

どの症状も比較的重い病気を抱えている場合が多いため、一刻も早く、動物病院で診察を受けていただきたいですが、どうしても早急に病院に行けないケースでは、なるべく安静にするよう心がけてください。
外に出る猫の場合
基本的に猫の外飼いは推奨できませんが、外に出る場合、交通事故などによる外傷はないか観察してください。外傷がない場合は、飼い主さんが触って痛がる場所がないか、ふらつき以外の神経症状(左右の瞳孔の違いやよだれの垂れ流し、震えや部分的な痙攣、うまくフードを食べることができないなど)はないかどうか、全身状態を観察してみてください。もし見られた場合はすぐ病院へ行きましょう。何も見られないときには、猫のことをしっかり観察しながら、ペット用のカゴなどに入れて、行動範囲を制限してみてください。このように行動範囲を制限することで、高いところから落ちて頭を打つなどの二次的なケガを防げるのはもちろん、一時的なふらつきの場合は、行動範囲を制限するうち、元のように歩けることもあります。
このケースでは、重篤な病気の可能性もあるため自宅であまり様子を見ることがすすめられません。また、神経的な異常の場合、診断にはCTやMRIなどの高度医療が必要になることが多いので、動物病院の診察を受けた上、先生としっかりと今後について相談しましょう。
