
犬の下痢は食事やストレス、冷えなどちょっとした生活の変化が原因で起こります。繰り返したり、血が混じっていたり、嘔吐や食欲不振が見られたりする場合は注意が必要です。今回は下痢が起こる理由から、薬やビオフェルミン、ヨーグルトなどの対処法について、目黒アニマルメディカルセンター/MAMeC院長の佐藤が解説します。
犬の下痢とは

下痢は体調変化のサインとして、飼い主さんが気づきやすい症状の一つです。腸の動き(ぜん動運動)が過剰になったり、腸の水分吸収が不十分だったり、逆に水分分泌が過剰になったりすることで「軟便」、そして「下痢便」になります。
その原因はさまざまですので、便の状態を観察したり、他に症状がないかを確認したりすることが重要です。出血を伴う下痢のほうが緊急性が高いと思うかも知れませんが、必ずしもそうとは言い切れません。
様子を見てもいい下痢
以下に該当する場合、1〜2日ほど様子を見て大丈夫です。軽度の急性下痢であれば2〜3日で症状は良くなります。腸内細菌叢が乱れてしまい慢性化する場合もあります。改善せず、悪化したり続いたりする場合は動物病院へ行くようにしてください。食事を変えた
ごはんを別の商品に変更しただけでなく、「いつもと違う味にした」「トッピングやおやつをいつもより多めに与えた」「急に手作りごはんを与えた」といった変化で下痢になる場合があります。これは人間のデトックスのように腸内細菌が変化することで起こり、一定期間慣れさせる期間が必要です。消化に悪い食事をした
さつまいもやとうもろこし、おからなど食物繊維が多い食材を食べたり、牛乳や脂の多い肉類、揚げ物などを食べたりして下痢になる場合があります。食べ物が傷みやすい夏は食中毒を起こしやすいため注意が必要です。環境の変化があった
ペットホテルに預けたり、引っ越し、旅行をしたりといった場所の変化や、子どもが生まれたり、同居動物が増えたりといった家族の変化、急に寒くなるなど季節の変わり目に多い気温の変化、トリミングや通院、来客などのストレスで下痢になる場合があります。動物病院に行くべき下痢
.jpg)
以下に該当する場合は、緊急性が高いため動物病院へ行くようにしてください。
誤飲・誤食をした
人間の食べ物や薬、小さなおもちゃなど家の中で起きることもありますし、散歩中に拾い食いをする場合もあります。消化に悪いだけでなく、中毒を起こしたり食道や腸で詰まったりすると大変危険です。すぐに来院していただければ応急処置を行うことができます。まずは動物病院に連絡して、「いつ」「何を」「どれくらい食べたのか」分かる範囲で伝えてください。
血が混じっている
血を見るとびっくりしてしまう飼い主さんも多いと思いますが、胃腸炎から寄生虫、腫瘍や単に肛門が切れただけなど原因はさまざまです。血の状態というより、出血が続いたり、食欲や元気が無かったりする場合に緊急性が高くなります。食欲や元気が無い
下痢だけでなく、食欲や元気が無い、嘔吐をしている、体を痒がっているといった症状が出る場合は、病気や感染症、アレルギーの可能性があります。放っておくと重篤化するかもしれませんので、すぐ動物病院に行きましょう。犬が下痢をする原因と対処法

下痢は大きく「小腸性」と「大腸性」の二つに分けられます。排便の様子や糞便の性状などから、おおよそ判別することが可能です。
小腸性下痢の場合
小腸に異常があると、栄養が吸収されず体重が減っていきます。便の頻度は通常と変わらないか少し多いくらいで、しぶる症状は認められません。食道や胃、十二指腸など上部消化管に出血があると、黒い便(タール便)が排泄されます。| 原因 | 対処法 | |
|---|---|---|
| 食事 | 質の悪いフードや古くなったフードなどの酸化した油 | 質の良いフード、ウェットフードなどへの変更 |
| 食物アレルギー | 除去食試験を受けて確定した場合は原因となる食材を避ける | |
| 感染症 | パルボ、ジステンパーなどのウイルス | 抗生物質の投与、対症療法など |
| 回虫、条虫、鉤虫、糞線虫、ジアルジア、コクシジウムなどの寄生虫 | 駆虫薬の投与 | |
| 基礎疾患 | 慢性腸炎、胃潰瘍、腫瘍、膵外分泌不全、肝疾患など | 各疾患の治療 |
大腸性下痢の場合
大腸性の場合は水分量の変化で起こるため、体重の変化はほとんど見られません。便の頻度は増え、ゼリー状や鮮血を含む便が排泄されることがあります。うんちが出ないしぶりが見られる場合もあります。| 原因 | 対処法 | |
|---|---|---|
| 食事 | 新しい食事に腸内環境が対応できていない | 元の食事に戻す。頻繁に変えたり、一気に変えたりせず、少しずつ置き換える |
| 食材に含まれる食物繊維が過剰 | さつまいもやとうもろこし、おからなど食物繊維の多い食材を避ける | |
| 食物アレルギー | 除去食試験を受けて確定した場合は原因となる食材を避ける | |
| 誤飲・誤食 | 吸着剤(活性炭)の投与、内視鏡による除去、開腹手術など | |
| 薬 | 抗生物質など | 乳酸菌製剤の服用 |
| ストレス | 環境の変化、ストレスによる過敏性腸症候群など | ストレス要因の除去 |
| 感染症 | サルモネラ、大腸菌、カンピロバクターなどの細菌 | 抗生物質の投与 |
| 鞭虫などの寄生虫 | 駆虫薬の投与 | |
| 基礎疾患 | 慢性腸炎(炎症性腸疾患)、腫瘍など | 各疾患の治療 |
病気が原因の場合
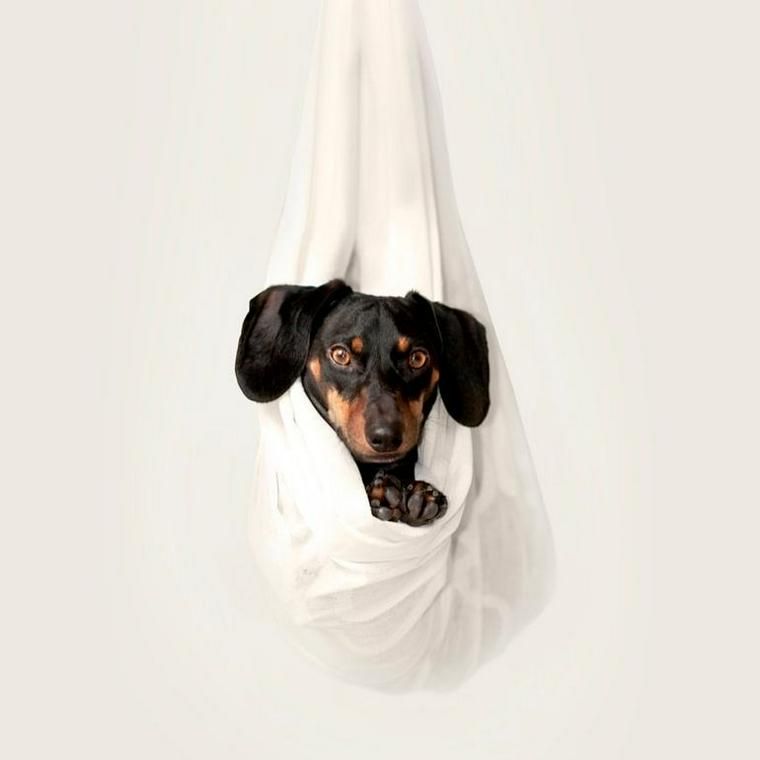
消化器疾患を患っている場合は、ほとんどの症例で下痢が起こります。下痢以外にも嘔吐や発熱、食欲不振、体重減少などの症状が認められることがあります。内分泌疾患でも下痢が多く、元気がなくなったり多飲多尿になったりする場合もあります。
腫瘍の場合、胃や小腸など上部消化管だと黒色便、肛門や大腸付近だと鮮血の付着がみられます。便が固くなったから問題ないと安易に判断しないでください。中にはポリープのような腫瘤性病変が存在する場合もあるため注意が必要です。
過敏性腸症候群と炎症性腸疾患
過敏性腸症候群(IBS)は、大腸に原因となる病気が無いにも関わらず、下痢や便秘などの症状が慢性的に続く疾患です。原因は不明ですが、ストレスが関係しているのではないかと考えられています。精神安定剤や食事療法で良くなることがあります。炎症性腸疾患(IBD)も、原因不明で下痢や嘔吐、体重減少が続きます。免疫反応が関係しているのではないかと考えられ、食事療法で良くなることがあります。どちらも「難治性下痢症」と呼ばれ、治療が難しい病気です。最近では、再生医療など新しい治療も導入されています。
自宅でできる下痢の対処法や注意点

私たちも食べ過ぎやちょっとしたストレスで下痢になるように、犬もちょっとしたことで下痢になる場合があります。食欲もあり、普段と変わらず元気にしているようであれば、以下のような対処法を試してみてください。
食事療法
食事を変えたことで下痢になった場合は、一定期間のデトックスですので、慣れさせることが大切です。一気に切り替えるのではなく、元の食事と混ぜながら慣れさせてあげましょう。下痢が治るまでは通常量を与えるのではなく、量を少なくして回数を増やし、ドライフードであればふやかしてあげるとお腹への負担が軽減されます。下痢が続くと水分が失われてしまうため、脱水を起こさないように水分はしっかり摂取させましょう。犬用のポカリスエットがベストですが、一時的であれば人間用のポカリスエットやOS-1などの経口補水液でも大丈夫です。

ペットスエット
Amazonで見る
Amazonで見る
人間用のポカリスエットは糖分が多いため、長期的に与えてしまうと肥満や糖尿病の原因になりますので注意してください。あげる目安は「体重 x 10ml」を1回であげてください。十分とは言えませんが、一時的に脱水を防ぐことはできます。
整腸剤

犬用の乳酸菌製剤が販売されていますので、それを整腸剤として飲ませるといいでしょう。
人間用のものであればビオフェルミンR(耐性乳酸菌整腸剤)、ビオフェルミンSを1日2回飲ませても大丈夫です。1回あたり小型犬なら1/4錠、中型犬は1/2錠、大型犬は1錠を目安にしてください。
ヨーグルトにも乳酸菌が含まれますが、効果は限定されるかもしれません。正常なときに予防や健康維持を目的として与えるのがいいでしょう。
絶水・絶食は獣医師の指示で
成犬であればお腹を休ませるため、半日〜1日の絶水や絶食を行うことがあります。脱水を予防するため皮下点滴や、状態が悪い場合は入院させて静脈点滴を実施します。悪化させたり別の問題を起こしたりする可能性がありますので、飼い主さんの判断では行わないようにしてください。
犬に正露丸®を与えるのは絶対NG
下痢をしている犬にも正露丸を飲ませようとする方がいますが、絶対にやめてください。正露丸などの胃腸薬には「クレオソート」という強力な消毒剤が含まれています。犬に飲ませると胃壁を荒らして消化器に強いダメージを与えてしまったり、消毒剤をうまく代謝できずに中毒状態になってしまう場合があります。
多頭飼いの場合は、下痢の子を隔離
下痢の原因が感染症の場合、同居動物に感染が広がる可能性があります。できる限り隔離して、糞便に近づけないようにしてください。犬の下痢の検査・診断方法
まずは十分に問診を行い、以下の項目について確認します。いま食べているフードや環境の変化、排便回数や便の硬さなどのメモを持参していただけると、よりスムーズに診断を進めることができます。- 下痢は急性か、慢性(3週間以上続く)か
- 食事の変更や盗み食い、異食、過食はあるか
- 異物、薬剤、毒物摂取の可能性はあるか
- 下痢以外の症状の有無(体重減少、食欲低下など)
- 寄生虫など感染の可能性はあるか
- 過去の治療歴
次に身体検査を行い、犬の状態を見ながら以下の検査項目を検討します。
- 糞便検査
- 血液検査
- X線検査
- 腹部超音波検査
- 内視鏡検査
糞便検査
新鮮便を持参していただくと糞便検査を行うことができ、感染症の診断に役立ちます。数gあれば充分な検査ができますので、ラップやビニールなど水分を吸収しないものに包んでお持ちください。まとめ

食事や環境の変化による下痢であれば様子見で大丈夫
誤飲や下痢以外の症状がある場合はすぐに病院へ
食事療法や整腸剤で改善する場合も
参考文献
- 佐藤 貴紀:犬の急病対応マニュアル,鉄人社
- 中島 亘:CLINIC NOTE 2012年10月号(No.87 )pp.7-22,インターズー
- 長谷川篤彦,辻本元監訳:スモールアニマル・インターナルメディスン 第3版 上巻,インターズー
- SA Medicine 66号 特集 治療シリーズ③ 消化器疾患,インターズー
【動画解説】犬の下痢の原因や対処法
YouTubeのPETOKOTOチャンネルでは、犬の下痢について解説した動画を公開しています。あわせてご覧ください。気になることがあれば専門家に聞いてみよう!

InstagramのPETOKOTO FOODSアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」を定期開催しています。愛犬のごはんについて気になることがある方は、ぜひご参加ください。
アカウントをフォローする
