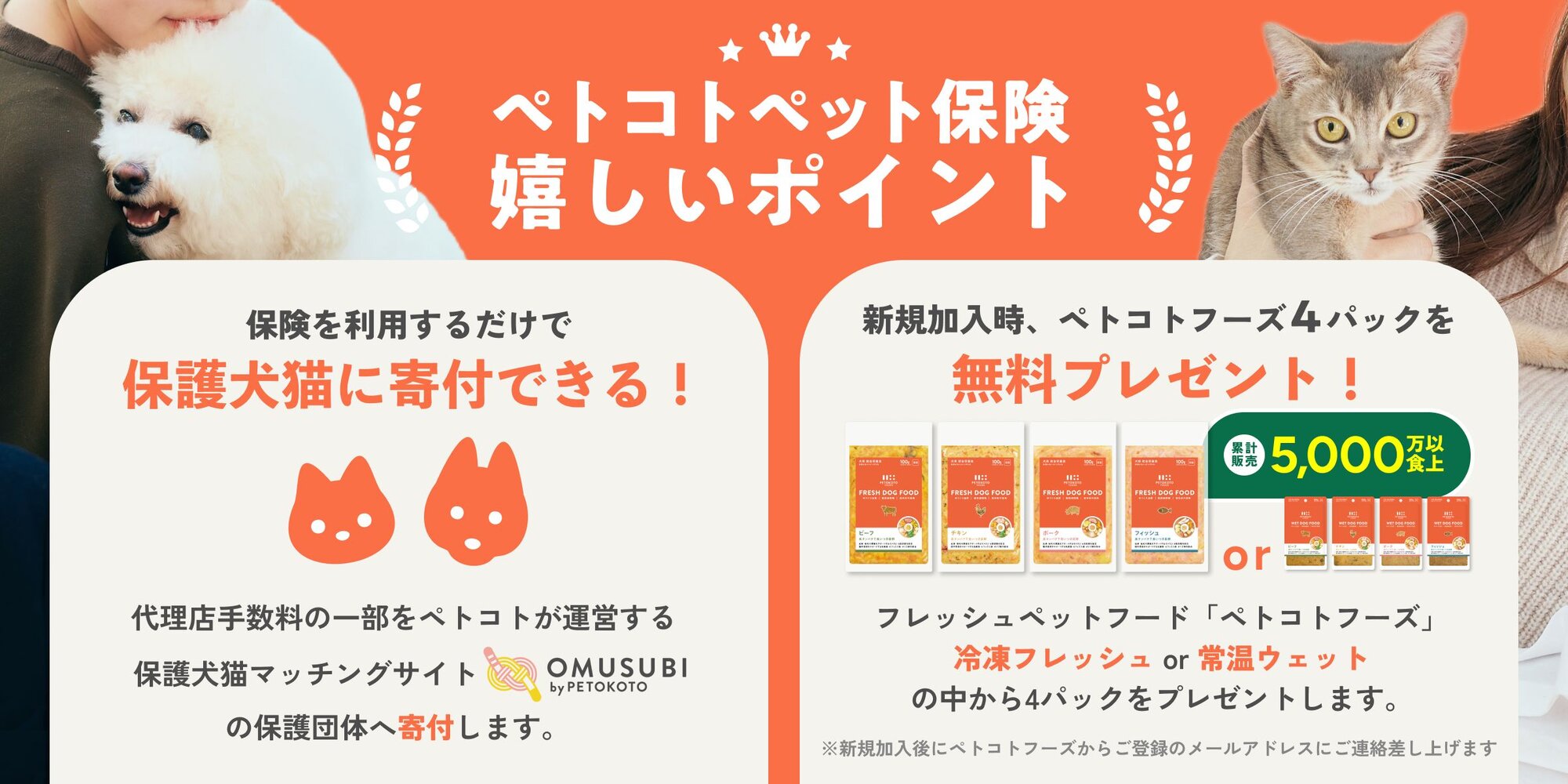愛猫がどんどん痩せて、気づいたらガリガリに痩せてしまった、ということはありますか?猫が痩せてくるにはさまざまな原因がありますが、その多くが命にも関わるような病気です。体重を計る機会はあまりないかもしれませんが、普段のスキンシップの中で痩せたことに気づくポイントは多くあります。今回は「高齢ではないのに」「食欲はあるのに」といった場合などに考えられる猫が痩せてしまう原因や、体型チェックのポイント、痩せすぎの場合の判断基準などをご説明します。
目次
食欲はあるのに猫が痩せる場合の原因

愛猫が食欲があるのに痩せてしまう場合は、一般的に以下の可能性があります。
- 必要カロリー量が違う
- 甲状腺機能亢進症
- サナダムシ(瓜実条虫)等の消化管内寄生虫
- 糖尿病
\動画もチェック!/
必要カロリー量が違う
キャットフードの裏面にあるカロリー量はあくまで目安の情報となります。具体的には、行動量や体型、避妊去勢、年齢などでも必要なカロリー量は変わります。そのため、まずは記載の目安量で与えた上で、体重を測りながら増減を見て、与える量を増やす・減らすことが大切です。甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモン(※)が過剰に産生される病気です。そうなることによって体の基礎代謝が上昇してしまうことで多食にも関わらず痩せる、嘔吐・下痢する、凶暴になるなどの行動の変化がみられます。※甲状腺ホルモンとは甲状腺から分泌され、一般に全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンのこと。
サナダムシ等の消化管内寄生虫
消化管内に寄生するさまざまな寄生虫は少数だとあまり症状は出しませんが、多数寄生されると栄養を横取りされたり、下痢をしやすくなり痩せてしまうことがあります。糖尿病
猫の糖尿病ではオスはメスの1.5倍発症しやすく、肥満や老齢がリスクとなります。ぶどう糖の消費を促進する作用のもつインスリンが不足することで発症し、適切な治療がないと重度の高血糖やケトアシドーシス(※)など生命に関わる状態に進行してしまうことも多い疾患です。※血液が酸性になること。高血糖状態になると、体はその代わりに脂肪を分解してエネルギーをつくり出します。このときに副産物としてつくり出されるケトン体が血液中に急に増える(高ケトン血症)ことで、血液が酸性になり(ケトアシドーシス)、体に異常が発生するというしくみ。
食欲がなく猫が痩せる場合の原因
食欲がなく痩せてしまう場合は、一般的に以下の可能性があります。- 口内炎や歯肉炎など口の中のトラブル
- 環境変化等によるストレス
- 高齢の場合は腎不全
- 誤飲により食欲不振
- 膵炎
口内炎や歯肉炎など口の中のトラブル
猫は慢性の歯肉炎が多い動物です。原因についてははっきりしていませんが、免疫不全やウイルスの感染の関与が考えられています。決定的な治療法はなく、歯石取りや細菌感染を防ぐための抗菌薬の投与などの対症療法で対応します。環境変化等によるストレス
猫は食に対して敏感で頑固なところがあり、環境が変わるとしばらくご飯を食べないことがあります。また夏場は暑さで食欲不振の場合もありますし、熱中症などの危険もあります。
高齢の場合は老衰か腎不全
老猫になるにつれてやはり体重は減少傾向になってきます。特に7歳からは高齢の域に入るので、7歳頃から数年かけて少しずつ体重が減ってくる場合は加齢の影響があるかと思われます。猫は犬と比べると暑さにも比較的強い生き物なので、一年を通じて一定の体型が保たれているのが理想です。また、猫は腎不全になりやすい動物でもあります。腎不全になると脱水や体に有害なタンパク質の代謝産物をおしっこにうまく排泄できなくなるため食欲が落ちてきます。
誤飲により食欲不振
紐状の異物やスポンジ、プラスチックバックのかけらなどを飲み込むと消化管のどこかで閉塞し、消化管の動きがストップします。この時は食欲不振の他に嘔吐も頻繁にみられます。膵炎
消化液を出す膵臓に炎症が起きると、激しい炎症が起き痛みを起こし食欲不振や嘔吐がみられます。適切な処置をしないと命を落とすこともあります。肥満した猫が何らかの原因で食事ができなくなり急激に痩せると、肝臓に脂肪が集まって肝リピドーシスになります。食欲不振のほか、神経症状や黄疸など重篤な症状に進行するので食欲がなくなったら様子をみずに早めに受診することが大切です。
猫が痩せすぎかを測る適正体型のチェック方法

5段階法と9段階法があり、5段階法ではBCS3が理想の体型です。9段階法ではBCS5が理想の状態ですが、基本的には評価基準は同じなので5段階法についてご説明します。これはお家でも確認できるので、ぜひ愛猫の体型をチェックしてみてください。

BCS1(痩せ)
助骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える状態。または首が細く、上から見て腰が深くくびれている状態のことを指します。横から見ると腹部の吊り上がりが顕著です。脇腹のひだには脂肪がないか、ひだ自体がありません。BCS2(やや痩せ)
背骨と助骨が容易に触れます。上から見て腰のくびれは最小、横から見て腹部の吊り上がりはわずかな状態を指します。BCS3(理想的)
助骨は触れますが、外から見ることができません。真上から観察すると肋骨の後ろにわずかなくびれが見えます。横から見ると脇腹には皮下脂肪と皮膚からできるひだが観察できます。BCS4(やや肥満)
助骨の上に脂肪がわずかに沈着していますが、助骨は容易に触れます。横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹は窪んでいます。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れていることに気づくでしょう。BCS5(肥満)
助骨や背骨は厚い脂肪に覆われて容易に触れません。横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られません。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れます。まずは猫との毎日のスキンシップの中で、その子の普段の脂肪のつき具合や食欲、ウンチの間隔などを観察するようにしてみてください。
猫は毛があるので見た目だけでは太った・痩せたの判断が難しく、またしょっちゅう体重を測る訳ではないので、コミュニケーションをとるために撫でている中で「少し骨が良く触れるな?」などを気にすると病気の早期発見にも繋がるでしょう。大体食欲がなくなって2週間くらい経つと痩せてくるので、注意してみてください。
また、1年に一度はワクチンや健康診断で動物病院を受診することをおすすめします。身体検査だけでも毎年正確な体重の推移がカルテに残りますし、雑音や体表にできものなどの異常がある時も対応してもらえます。猫は3ヶ月で大体人間に換算すると1歳年をとるといわれているので、自宅でも3ヶ月に1度は猫の体重を測ってあげるとよいでしょう。
猫を抱っこした状態で人間用の体重を測ります。その後、人間だけの体重を測り、猫と一緒の体重から引けば大体の猫の体重がわかります。体重減少の目安ですが、もとの体重から「何パーセントくらい減ったか?」を考えます。
例えば1ヶ月から3ヶ月で、前回の体重から3%から5%減っていれば受診をおすすめします。例えば3kgの猫だと90〜150gの減少が数ヶ月でみられれば5%の減少なので診察をおすすめする状態ということです。5kgの猫なら150〜250gくらいです。
猫が痩せる場合の対処法

食欲がある場合で特に健康上も症状が見られない場合(猫は痛みに強い動物です)、カロリー量を見直したり、キャットフード・ご飯を変更してみることをおすすめします。
もし、若いのに健康上で症状が出ていたり、不安がある場合は、動物病院で診てもらうようにしましょう。病気が隠れている可能性があります。痩せていなくても数日単位で急に食欲が落ちた時は受診をおすすめします。また、食欲があっても触ったりしていて「肋骨がよく触れるな」と思った時や、1〜3ヶ月で3〜5%以上の体重減少があった時も一度獣医師に相談することをおすすめします。
愛猫が痩せる場合は原因を考えて、相談すること

猫が痩せたり食欲がなくなってくるのは原因に関わらず重篤な状態に陥ることがよくあります。特に猫は体重が人間よりもだいぶ軽いので、数10gの変化しかないので気に留めなくても、猫にとっては大きな変化である場合があります。
BCS3のときの愛猫の体重を覚えておき、そこから3%以上の変化があれば受診の目安とするとよいかもしれません。また食欲がないときは、体重変化が明らかにみられなくても早めに受診することが大切です。
参考文献
- 岩崎利郎 / 辻本元 / 長谷川篤彦監修(2014)『獣医内科学』文英堂出版
- 左向敏紀 / 阿部又信著(2015)『臨床栄養学』インターズー
飼い主の“もしも”に備えて。ペットの未来を考える選択肢

飼い主に万が一のことがあったとき、大切な家族である愛犬・愛猫の暮らしはどうなるのか——。
「みらいの約束」は、そうした不安に向き合いたい方に向けたサービスのひとつです。
「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか」。そんな想いを持つ飼い主にとって、ペットのこれからを考えるきっかけのひとつになるはず。サービスの内容や詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。