
大豆は犬が食べても基本的に問題ない食材ですが、「乾燥大豆」や「節分の煎り大豆」は注意が必要です。消化不良や嘔吐、アレルギー症状のリスクがあり、特に小型犬は喉に詰まる危険も。水煮大豆や豆腐、納豆などの加工食品なら犬も食べやすく、おやつやトッピングにおすすめです。本記事では、犬に大豆を与えるメリット・注意点・豆まき後の誤食対処法までわかりやすく解説します。
犬は大豆を食べても大丈夫!

大豆は栄養価の高い食材で、人間だけでなく犬にとっても健康維持に役立つ成分が多く含まれています。ただし、与え方や調理方法によっては体に負担がかかる可能性もあるため、正しい知識をもって与えることが大切です。
加熱すれば基本的にOK!ただし注意も必要
犬に大豆を与える場合、加熱済みであれば基本的に食べても大丈夫とされています。加熱することで消化に悪い成分が無効化され、犬の体に負担をかけにくくなります。
ただし、犬によっては体質的に大豆が合わない場合もあります。アレルギーや下痢などの症状が出るケースもあるため、最初はごく少量から始めて様子を見るようにしましょう。
生の大豆はNG!中毒や消化不良のリスク
加熱されていない生の大豆には、「トリプシン・インヒビター」という成分が含まれており、これは消化酵素の働きを妨げてしまいます。そのため、生の大豆をそのまま食べると消化不良や嘔吐・下痢などのトラブルを起こすリスクがあります。
この成分は熱に弱いため、大豆を与えるときは必ず加熱処理されたものを使用することが鉄則です。とくに節分の豆まきで使われる煎り大豆などは硬く、消化不良や喉詰まりの原因にもなるため注意が必要です。
犬が大豆を食べるメリットとは?
大豆には、良質な植物性タンパク質をはじめ、カルシウムやビタミンB1、大豆イソフラボン、食物繊維など、犬の健康維持に役立つ栄養素が豊富に含まれています。
筋肉や被毛、皮膚の健康を支える栄養素がバランスよく含まれているため、加熱された大豆を適量取り入れることは栄養補助として有効です。また、大豆に含まれる食物繊維は腸内環境の改善にもつながります。
大豆に含まれる主な栄養素と働き
大豆は「畑の肉」とも呼ばれるほど栄養豊富な食材で、犬の健康維持にも役立つ成分が多数含まれています。ただし、摂取量や体質によっては注意が必要な成分もあります。大豆に含まれる代表的な栄養素とその働きについて見ていきましょう。
| エネルギー | 429kcal |
|---|---|
| 水分 | 2.5g |
| タンパク質 | 37.5g |
| 脂質 | 21.6g |
| 糖質 | 13.9g |
| カリウム | 2000mg |
| マグネシウム | 240mg |
| リン | 710mg |
| 葉酸 | 260μg |
| 食物繊維 | 19.4g |
| 栄養素 | 特徴 |
|---|---|
| カリウム | 過剰な塩分を排出してナトリウムとのバランスを保ち、血圧を安定させる効果があります。腎臓病の場合は過剰(高カリウム血症)になり心臓にダメージを与えてしまいます。摂取量に注意が必要です。 |
| マグネシウム | 骨を作り心臓を動かすために欠かせないミネラルで、不足すると骨粗鬆症や不整脈などの心疾患につながります。過剰摂取ではストルバイト結石のリスクを高めるため、摂取量に注意が必要です。 |
| リン | 骨や歯の形成、エネルギー代謝に重要な役割を果たしています。腎臓病の犬猫ではリンの排出が正常に行われず腎臓病を悪化させてしまうため制限が必要です。 |
| 葉酸 | 体の細胞の生まれ変わりや成長をサポートするという大切な役割を持ち、「造血のビタミン」と呼ばれます。不足すると貧血や免疫力の低下につながります。 |
| 食物繊維 | 腸内細菌のエサとなって腸内環境を改善したり、食後の血糖上昇をゆるやかにして糖尿病を予防したりします。水溶性は満腹感の持続や下痢の改善、不溶性は便秘の改善などの効果が期待できます。 |
タンパク質・カルシウム・ビタミンB1で健康サポート
大豆には、筋肉や皮膚、被毛、血液などを作るために必要なタンパク質が豊富に含まれています。動物性タンパク質と比べても質が高く、植物性でも十分に補える栄養価です。
また、カルシウムは骨や歯の健康を保つために不可欠で、成長期の犬やシニア犬にとって特に重要な栄養素です。ビタミンB1はエネルギー代謝に関わる働きを持ち、日常の活力維持に貢献します。
イソフラボンの抗酸化作用とアンチエイジング効果
大豆に含まれる大豆イソフラボンは、細胞の老化を防ぐ抗酸化作用を持つことで知られています。とくに、シニア犬のアンチエイジングや被毛の美しさを保つサポートとして期待できます。
カリウム・マグネシウム・リンなど注意したい栄養素
大豆にはミネラルも豊富に含まれています。たとえば、カリウムは塩分を排出して血圧のバランスを保つ働きがありますが、腎臓に疾患のある犬には注意が必要です。
さらに、マグネシウムやリンは骨や歯の形成に関わる重要な栄養素ですが、摂りすぎると尿路結石や腎臓病のリスクを高めることがあります。健康状態によっては制限が必要な場合もあるため、獣医師と相談しながら取り入れましょう。
犬に大豆を与えるときの注意点

大豆は栄養豊富で健康に役立つ一方で、与え方を間違えるとアレルギーや消化不良などのトラブルを招くことがあります。
01アレルギー反応に注意(皮膚トラブル・下痢・嘔吐など)
犬が大豆を食べた際にアレルギーを引き起こすことも稀にあります。皮膚のかゆみや赤み、下痢、嘔吐などの症状が見られる場合は、アレルギーの可能性を疑いましょう。
初めて大豆を与える場合は、ごく少量からスタートし、食後の体調をよく観察することが大切です。不安がある場合は、獣医師に相談のうえで検査を受けるのもひとつの方法です。
02消化不良を防ぐには?加熱・調理の工夫が重要
大豆はそのままだと硬く、犬にとっては消化しづらい食材です。特に小型犬や胃腸が弱い子には負担となるため、柔らかく煮る・すりつぶすなどの調理が必要です。
なお、「水煮大豆」や「おから」などの加工済みの食品は、与えることができます。形が残るほど固い煎り大豆は避けましょう。
03節分の豆や煎り大豆はNG!喉詰まり・腸閉塞のリスク
節分で使われる煎り大豆は、非常に硬く、消化に時間がかかるうえに喉に詰まりやすいため危険です。特に小型犬は誤飲による喉詰まりや腸閉塞のリスクが高いため、注意が必要です。
節分の時期は落ちた豆を拾い食いしないよう、豆まきの後の掃除を徹底する、犬を別室に移動させるなどの工夫をしましょう。
04大豆に含まれる注意すべき成分
大豆には健康効果のある成分が多く含まれていますが、犬にとっては摂りすぎると害となる成分もあります。
| 成分名 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| レクチン | 腸内にくっついて栄養吸収を妨げ、下痢や嘔吐の原因になることがあります。加熱や発酵で抑えられるため、加熱済みの大豆食品を選びましょう。 |
| フィチン酸 | 体内のミネラルと結合して排出を促す性質があり、カルシウムや鉄分の吸収を阻害する可能性があります。 |
| サポニン | 抗酸化作用がある一方で、大量摂取により腸の炎症や下痢の原因になることも。適量の摂取が大切です。 |
これらの成分も、過剰摂取しなければ基本的には心配いりませんが、継続的に与える場合は獣医師に相談のうえで量を調整しましょう。
犬におすすめの大豆加工食品

大豆はそのまま与えるよりも、加熱加工された食品を選ぶことで安全性や消化性が高まります。特に市販されている無調整の加工食品は、日常的に活用しやすく、トッピングやおやつとしても優秀です。
犬に与えるのにおすすめの大豆加工食品としては、豆腐・納豆・おから・きな粉・豆乳・水煮大豆などがあります。これらは加熱または発酵により、消化にやさしく仕上げられているため安心して利用できます。
ただし、人間用に味付けされているもの(醤油入り豆腐や甘いきな粉など)は塩分や糖分が過剰なことがあるため、無調整タイプを選ぶようにしましょう。
大豆入りの犬用のおやつの選び方
大豆やおからを使った犬用のおやつも多く販売されています。選ぶ際は以下のポイントに注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無添加・保存料不使用 | 余計な添加物が少ない方が安心です。 |
| アレルギー表示の明記 | アレルギー対応の記載があるか確認しましょう。 |
| 嗜好性よりも安全性 | 愛犬が喜ぶことも大切ですが、まずは安全性を優先してください。 |
手作りのおやつにきな粉やおからを取り入れるのも良い方法です。与える前に必ず無糖・無塩であることをチェックしましょう。
おやつやトッピングとして与える量と目安
加工された大豆食品でも、与えすぎは肥満や栄養バランスの乱れの原因となります。基本的には、おやつやトッピングとして取り入れ、1日に与える総カロリーの10%以内に収めるのが理想です。最適カロリー量は「ペトコトフーズ」の食事量計算機(無料)で簡単に確認できます。
愛犬の食事量を計算する大豆を使った犬用フードもある!

市販のドッグフードにも、大豆を使った商品が増えてきています。特に「おから」や「大豆たんぱく」を利用したフードは、消化に配慮しながら栄養バランスも整えられており、健康維持やダイエット目的にもおすすめです。
大豆を使用した総合栄養食とは?
総合栄養食とは、犬に必要な栄養素をバランスよく含んだフードのことです。近年では、動物性たんぱく源だけでなく、大豆をベースにした植物性たんぱくも活用されており、アレルギー対策や低脂質志向の家庭に選ばれています。
大豆由来の総合栄養食は、動物性原料に比べて脂質が抑えられているものも多く、肥満気味の犬やシニア犬にも適しています。ただし、原材料欄をよく確認し、添加物や塩分が多く含まれていないかをチェックしましょう。
ペトコトフーズの「おから入り」フードの魅力
ペトコトフーズの「ポークメニュー」には、国産のおからが使用されており、腸内環境のサポートや食物繊維による便通の改善が期待できます。
香料・保存料を使わず、新鮮な国産食材だけで作られているため、安心して毎日のごはんとして与えることができるのが特徴です。初回限定のお試しプランもあるので、気になる方はチェックしてみましょう。
意図せず犬が大豆を食べてしまったときの対処法
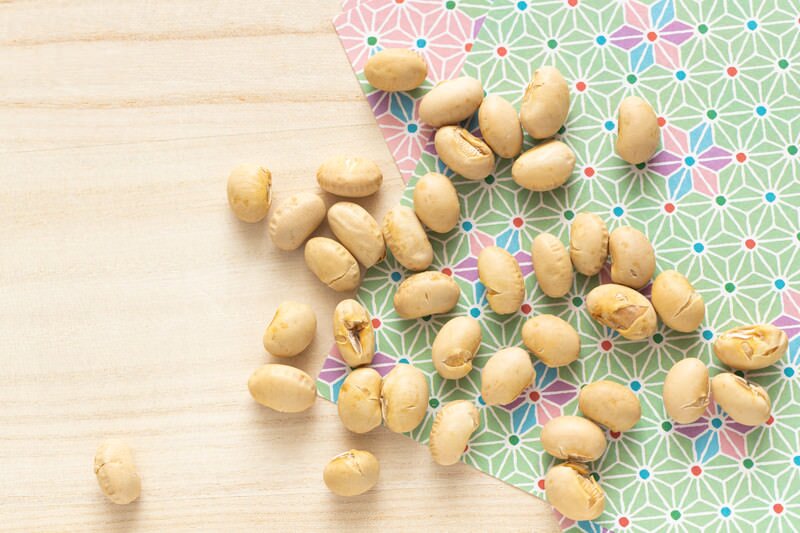
節分や料理中など、思いがけないタイミングで犬が大豆を口にしてしまうこともあります。特に煎り大豆や生の大豆はリスクがあるため、何を・どれくらい食べたかを確認することが大切です。以下のポイントに沿って、冷静に対応しましょう。
節分豆を食べた!まず確認すべきポイント
節分の豆まきで落ちた煎り大豆を犬が食べてしまうケースは少なくありません。煎り大豆は硬く、消化がしにくいため、喉に詰まらせたり腸閉塞を引き起こすリスクがあります。小型犬や高齢犬は特に注意が必要です。
まずは、どのくらいの量を食べたか、丸飲みしていないかなどを確認しましょう。大量でなければ経過観察で済むこともありますが、いつもと様子が違う・苦しそうにしている場合はすぐに動物病院へ。
下痢・嘔吐などの症状が出たらどうする?
大豆の摂取によって、下痢・嘔吐・お腹の張り・軟便といった症状が出ることがあります。特に加熱が不十分な状態で食べたり、煎り大豆を大量に食べたりすると、消化器に負担がかかりやすくなります。
まずは愛犬の様子をよく観察してください。元気があり、食欲もあるようであれば、以下のような自宅でのケアを試すことができます。
- 食事を1食分抜く(子犬を除く)ことで胃腸を休める
- その後は消化に良いごはんを、少量ずつ回数を分けて与える
- ドライフードならふやかす、または柔らかい流動食に切り替える
- 水分補給を忘れずに(脱水予防には犬用経口補水液が効果的)
ただし、嘔吐を繰り返す・水を飲んでも吐く・ぐったりしているなどの症状がある場合は、すぐに病院を受診してください。絶食・絶水は獣医師の指示があるとき以外は避け、悪化を防ぐ判断が必要です。
動物病院へ連れて行く判断の目安
以下のような状態が見られた場合は、飼い主の判断で様子見せずに動物病院を受診してください。
- 嘔吐を何度も繰り返す、または吐きそうで吐けない
- 下痢が長引いている、血が混ざっている、臭いが強い
- 元気がなく、ぐったりしている・寝たまま動かない
- 食欲がまったくない、水分も摂らない
- お腹を触ると嫌がる、背中を丸めてうずくまる
誤食の可能性がある場合や、原因がはっきりしないときでも、異常があればすぐに受診しましょう。何を・どれくらい食べたかをメモして伝えると、診察がスムーズになります。
まとめ

大豆は犬にとって栄養価の高い食材ですが、与え方や量に注意が必要です。加熱されていれば基本的には問題ありませんが、生の大豆や煎り大豆、過剰摂取は消化不良や体調不良の原因になります。
特にアレルギーがある犬や、腸が弱い犬、高齢犬には慎重に与えることが大切です。初めて与える際は、少量から様子を見て、下痢・嘔吐・皮膚トラブルなどがないかを確認しましょう。
大豆を安全に取り入れるには、ペトコトフーズのような、栄養バランスに優れたフードを活用するのもおすすめです。愛犬の体調や年齢に合わせて、適切に大豆を取り入れてあげてください。
参考文献
- 阿部又信(2008)『小動物栄養学』ファームプレス
犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。
1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。
2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。
3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。
この記事の監修者

ニック・ケイブ(Nick Cave)獣医師
米国獣医栄養学専門医・PETOKOTO FOODS監修
マッセー大学獣医学部小動物内科にて一般診療に従事した後、2000年に獣医学修士号を取得(研究テーマ:犬と猫の食物アレルギーにおける栄養管理)。
2004年にはカリフォルニア大学デービス校で栄養学と免疫学の博士号を取得し、小動物臨床栄養の研修を修了。同年、米国獣医師栄養学会より米国獣医栄養学専門医に認定。
世界的な犬猫の栄養ガイドラインであるAAFCOを策定する WSAVA の設立メンバーであり、2005年より小動物医学および栄養学の准教授としてマッセー大学に復帰。
家族とともに犬2匹・猫・ヤモリと暮らしながら、犬猫の栄養学の専門家として研究・教育に携わっている。

