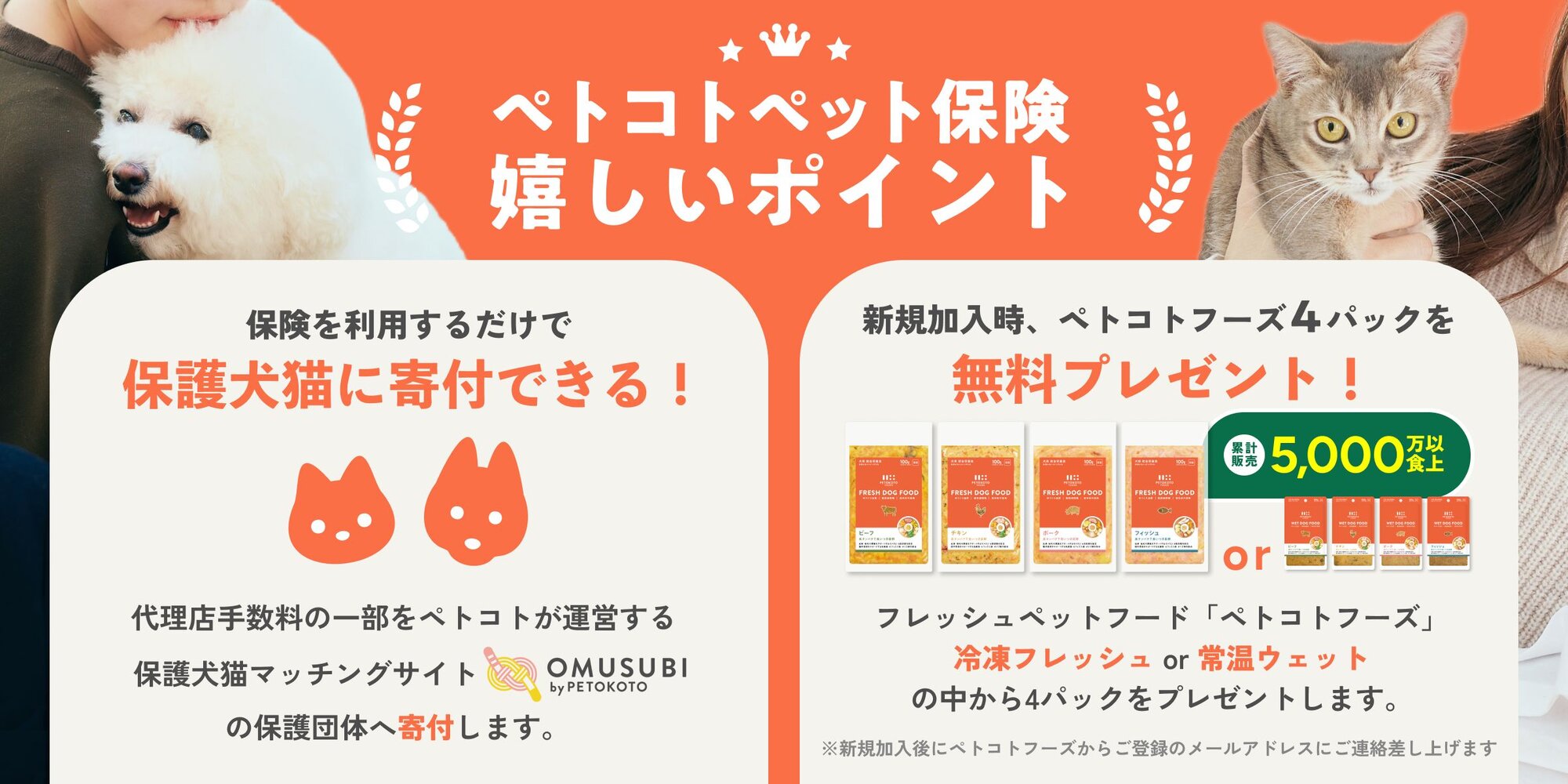一般的に猫は寒がりな動物です。その理由は猫の歴史を紐解けば見えてきます。今回は、そんな寒がりな猫のルーツや猫が寒いと感じる温度・寒がっているときのサインなどを解説します。
目次
※本稿はアフィリエイト広告を利用しています。
猫は寒がり?

猫は、砂漠地帯に住んでいるリビアヤマネコを祖先に持つ動物です。
猫の祖先が住んでいた砂漠地帯よりも日本の夏は湿度が高いため、日本の暑さに耐性があるとはいえませんが、一般的には水や寒さはあまり得意ではなく、寒がりな猫は多いです。
寒さに強い猫種
寒がりな猫ですが、猫種によっては「アンダーコート」と「オーバーコート」という二重構造の被毛である「ダブルコート」で守られた種類がいます。オーバーコートは冷たい外気から身体を守り、その下にあるアンダーコートが身体が持つ熱を逃さないようにします。
ダブルコートを持つ猫は、比較的寒さに強い猫種です。以下、代表的なダブルコートを持つ猫種を紹介します。
- メインクーン
- スコティッシュフォールド
- ノルウェージャンフォレストキャット
メインクーン

オスは成長すると8kgを超える場合もあるメインクーンは「大きな猫」としても世界的に有名です。
長いオーバーコートの中にアンダーコートをたくわえています。
スコティッシュフォールド

垂れ耳の童顔が特徴のスコティッシュフォールドは、根強い人気のある猫種です。
原産地であるスコットランドは、冬になると氷点下になることもあります。毛の長さには個体差がありますが、ダブルコートを持つことから寒さには強いといわれています。
ノルウェージャンフォレストキャット

azumona.catさん Thanks!!
優雅になびく長い毛を持ち、近年日本でもよく見られるようになってきました。
猫が寒いと感じる温度

具体的に猫にとって過ごしやすい温度は、20度〜28度ほどとされています。
湿度や猫種によっても多少異なりますが、猫が寒いと感じる温度は20度以下、暑いと感じる温度は28度以上といえます。
そのため、冷暖房をつける際は、室内の温度が25度程度になるよう、設定温度を調整しましょう。これ以上低いと夏場であっても寒がることがあるので、設定温度には注意しましょう。
猫が寒いときのサイン

- 丸くなる
- 運動量が減る
- 水を飲まなくなる
猫の行動から寒がっているかどうかを知ることができます。
ただし、普段との違いがわからないと見分けるのが難しいため、寒くない時期からの観察も欠かせません。
丸くなる
普段から丸くなって寝る猫も多いですが、普段は伸びて寝る場所などで丸くなっている場合や、活動している時間帯に丸くなっている場合には、寒いと感じている可能性があります。運動量が減る
丸くなると関連している部分もありますが、寒いと遊ばなくなったり、移動距離が短くなったりします。日向ぼっこが好きなのに窓際に近寄らず、家の奥の方から動きたがらないこともあります。
水を飲まなくなる
食欲はあるのに水を飲まなくなるのは、寒いときにみられる典型的な行動の一つです。これは病気を引き起こす原因にもなるので注意が必要です。寒さ対策を施しても改善されない場合は、まだ寒いと感じているか、獣医師に診てもらう必要がある可能性もあります。
寒がりな猫の寒さ対策

本格的な冬が来る前には冬毛に生え変わったり、食欲が増えたりと、自分で冬支度を始める習性も持つ猫ですが、必要なものは飼い主が用意し、環境を整えましょう。
エアコンで温度調節
室温は、25度前後に保つのが理想です。ガスや電気ストーブでも温度調節は可能ですが、やけどなどの事故につながる恐れがあるため、より安心なエアコンがおすすめです。エアコンが難しいという場合は、猫が暖房機器に触らないよう、フェンスを設けるなどの工夫をしましょう。
湯たんぽを用意する
湯たんぽは、やけどの心配はなく、安心して与えられます。くれぐれも、柔らかい素材ではなく硬い素材のものを選び、蓋はきちんと閉め、使用前には水漏れなどの不具合がないかのチェックをしましょう。
\おすすめグッズはこちら/
冬用の布団を設置する
夏と冬で機能が異なるベッドがあるため、それぞれの季節に合わせて使うのがおすすめです。冬は防寒効果のあるベッドを用意してあげましょう。湯たんぽと組み合わせての対策も効果的です。
ベッドは床から離れた場所に置くと下からの冷気を受けにくくなります。愛猫のお気に入りの場所の中でも、寒さを感じにくい場所に設置してあげましょう。
\おすすめグッズはこちら/
猫の寒さ対策で注意したいこと

こたつの使い方
こたつは、猫にとって要注意な暖房器具です。こたつの中で暑さに気づかず、眠り続けると熱中症を発症する恐れがあります。熱中症だけでなく、長時間熱に当たることで低温やけどになる恐れも。
「長時間猫から目を離さない」「こたつの電源をまめに切る」「ときどきこたつから猫を離す」など、少しの工夫でこれらのリスクを軽減することができます。
こたつに限らず、ホットカーペットなどにも共通して言えることなので、今一度、家の暖房機器の使い方を見直してみましょう。
室温を上げすぎない
暑すぎるのもよくありません。夏に発症しやすい脱水症状や熱中症にかかってしまうこともあります。部屋全体を暖めるために一部が高温になることもありますが、その場合は、猫が一人で行き来ができる場所に温度の低い部屋も用意しておきましょう。
寒さが原因で猫が発症しやすい病気やケガ

猫風邪
通称「猫風邪」と呼ばれる、風邪のような症状が見られる病気です。ウィルスなどが原因で発症するものですが、ストレスや寒さによって免疫力が下がると、発症するリスクが高くなります。
尿路結石症
寒くて水を飲む量が減ると、トイレに行く回数が減り尿の濃度も高くなるため、結晶ができやすくなります。水を飲む量が減る場合、食事に含まれるマグネシウムなどのミネラルを制限することも大切ですが、まずは水を置く場所を増やすなどの工夫で、水を飲むように促しましょう。
やけど・低温やけど
暖房機器を使う上で、避けては通れないリスクです。「熱くなる部分に近づけないようにする」「こまめに電源を消す」「あまり長時間同じ場所にいさせない」などの配慮しましょう。また、意外な盲点でもあるお風呂場は、湯船の蓋で温まっている猫が、誤って熱いお湯に落ちないように注意が必要です。
寒さに備えて準備をしよう

寒いときのサインは「丸くなる」「運動量が減る」「水を飲まない」などがあります
有効な寒さ対策は「湯たんぽ」「冬用の布団を用意する」などです
寒さによって「猫風邪」「尿路結石症」「やけど・低温やけど」になりやすくなります
そんな猫たちが安全に、ストレスフリーで寒さをしのげるように、飼い主さんは環境を整えてあげてくださいね。
飼い主の“もしも”に備えて。ペットの未来を考える選択肢

飼い主に万が一のことがあったとき、大切な家族である愛犬・愛猫の暮らしはどうなるのか——。
「みらいの約束」は、そうした不安に向き合いたい方に向けたサービスのひとつです。
「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか」。そんな想いを持つ飼い主にとって、ペットのこれからを考えるきっかけのひとつになるはず。サービスの内容や詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。