
犬も肥満になると病気のリスクを高め、寿命を縮めてしまいます。早めのダイエットをおすすめしますが、病気が原因のケースもあり注意が必要です。今回は肥満の見分け方からフードの与え方、子犬期やシニア(老犬)期の考え方まで解説します。
目次
犬が太る・肥満は寿命が短くなる原因に

アメリカ・ネスレリサーチセンターも同様に、ラブラドールレトリーバーを対象にした調査で、肥満の犬と正常な犬で寿命に2年近い差が出たことを報告しています(※2)。
肥満は見た目の問題だと楽観的に考える飼い主さんが少なくありません。しかし、見た目以上に体に悪影響を与えているということを理解していただければと思います。
※参照1:『Association between life span and body condition in neutered client‐owned dogs』(Journal of Veterinary Internal Medicine)、参照2:『Diet restriction and ageing in the dog: major observations over two decades』(British Journal of Nutrition)
犬が太る・肥満になる原因

01【犬の肥満の原因】ごはんの量が多い
いつもごはんの量を正確に量っていますか? 知らず知らずのうちに、量が増えている場合があります。私たちからすればちょっとした誤差でも、体が小さい犬には大きな誤差になっているかもしれません。よく太ったらドッグフードのせいと考えがちですが、一番重要なことはカロリー管理です。
ごはんは適切な量でも、おやつを与え過ぎているケースもよくあります。ご家族の中にこっそりあげている人がいる場合もありますので、家族全員がしっかり肥満のリスクを理解する必要があります。
02【犬の肥満の原因】運動量が少ない
毎日しっかり散歩できているでしょうか?「小型犬で家の中を走り回ってるから毎日じゃなくても大丈夫」と言う飼い主さんがいるかもしれませんが、散歩は全ての犬に必要です。何か問題があってうまくできない場合は、ドッグトレーナーを頼るようにしましょう。
外に出るといろいろな匂いがして、いろいろな出会いがあって、散歩は犬にとって毎回が大冒険です。刺激を受けることはストレス発散にもなりますので、散歩は欠かさないようにしてください。
03【犬の肥満の原因】病気
太る病気として、「甲状腺機能低下症」と「副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)」という2つのホルモンの病気(内分泌疾患)が挙げられます。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症になった場合、基礎代謝エネルギーが低下することで体重が増加していきます。これといった気付きやすい症状はありません。「なんとなく元気が無い」「なんとなく顔に覇気が無い」などがサインとなります。
副腎皮質機能亢進症
クッシング症候群とも呼ばれる副腎皮質機能亢進症は、腎臓の近くにある副腎と呼ばれる内分泌腺が過剰に働いている状態です。食事量が増えることで体重が増加したり、飲水量や尿量が増加したり、腹筋の筋肉が薄くなることで落ちてお腹がぽっこり出てきたりします。
他にもお腹に水が溜まってしまう病気で太って見えることがあります。さらに、肝臓が腫大(膨張)することで太ったように見えることもあります。
04【犬の肥満の原因】年齢や体調の変化
運動量が低下すれば体重が増えますが、その原因は散歩やドッグランに行く回数が減ったということだけではありません。体が痛くて散歩に行けない、体がしんどくて動けないといった隠れた病気が原因の場合があります。
普段と違いがないか注意して見てあげてください。日頃から体を触るようにすることで、腫瘍や痛みのある場所に気づきやすくなります。
去勢・不妊手術
去勢や不妊手術を行うと基礎代謝エネルギーが低下します。術後は食事量を30%減にすべきだといわれています。ただ、個体差があり太ってしまうケースもありますので、獣医師に相談しながらコントロールしてあげてください。
犬の肥満で起こる病気

さらに、「免疫力を下げる」「臓器に脂肪が沈着して機能が弱る」「体重が増えてその重みが関節に負担をかける」など、肥満になると体中で良くないことが起こります。また、脂肪で喉が逼迫され、呼吸が浅くいびきをかくこともあります。
具体的な病気としては、皮膚病や膵炎、糖尿病になることがわかっています。そして心臓病の悪化を招いたり、体重の増加により変形性関節症の症状が酷くなるなどが挙げられます。
愛犬が太っていると思ったら早めに動物病院へ行き、太る原因を突き止め、ダイエットさせることをオススメします。
犬の肥満の見分け方・肥満度チェック方法

5段階評価の3が理想の体型で、飼い主さん自身で確認することができますので、ぜひ愛犬の体型をチェックしてみてください。
 参照:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン』(環境省)
参照:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン』(環境省)
外に出るといろいろな匂いがして、いろいろな出会いがあって、散歩は犬にとって毎回が大冒険です。刺激を受けることはストレス発散にもなりますので、散歩は欠かさないようにしてください。
03【犬の肥満の原因】病気
太る病気として、「甲状腺機能低下症」と「副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)」という2つのホルモンの病気(内分泌疾患)が挙げられます。甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症になった場合、基礎代謝エネルギーが低下することで体重が増加していきます。これといった気付きやすい症状はありません。「なんとなく元気が無い」「なんとなく顔に覇気が無い」などがサインとなります。副腎皮質機能亢進症
クッシング症候群とも呼ばれる副腎皮質機能亢進症は、腎臓の近くにある副腎と呼ばれる内分泌腺が過剰に働いている状態です。食事量が増えることで体重が増加したり、飲水量や尿量が増加したり、腹筋の筋肉が薄くなることで落ちてお腹がぽっこり出てきたりします。他にもお腹に水が溜まってしまう病気で太って見えることがあります。さらに、肝臓が腫大(膨張)することで太ったように見えることもあります。
04【犬の肥満の原因】年齢や体調の変化
運動量が低下すれば体重が増えますが、その原因は散歩やドッグランに行く回数が減ったということだけではありません。体が痛くて散歩に行けない、体がしんどくて動けないといった隠れた病気が原因の場合があります。普段と違いがないか注意して見てあげてください。日頃から体を触るようにすることで、腫瘍や痛みのある場所に気づきやすくなります。
去勢・不妊手術
去勢や不妊手術を行うと基礎代謝エネルギーが低下します。術後は食事量を30%減にすべきだといわれています。ただ、個体差があり太ってしまうケースもありますので、獣医師に相談しながらコントロールしてあげてください。犬の肥満で起こる病気

さらに、「免疫力を下げる」「臓器に脂肪が沈着して機能が弱る」「体重が増えてその重みが関節に負担をかける」など、肥満になると体中で良くないことが起こります。また、脂肪で喉が逼迫され、呼吸が浅くいびきをかくこともあります。
具体的な病気としては、皮膚病や膵炎、糖尿病になることがわかっています。そして心臓病の悪化を招いたり、体重の増加により変形性関節症の症状が酷くなるなどが挙げられます。
愛犬が太っていると思ったら早めに動物病院へ行き、太る原因を突き止め、ダイエットさせることをオススメします。
犬の肥満の見分け方・肥満度チェック方法

5段階評価の3が理想の体型で、飼い主さん自身で確認することができますので、ぜひ愛犬の体型をチェックしてみてください。

参照:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン』(環境省)
| BCS1 | 痩せ | 助骨、腰椎、骨盤が容易に見え、触っても脂肪がわからない状態。腰のくびれと横から見た際の腹部の吊り上がりが顕著です。背骨がゴツゴツと見える場合もあります。 |
|---|---|---|
| BCS2 | やや痩せ | 助骨が容易に触れます。上から見て腰のくびれが顕著、横から見て腹部の吊り上がりも明瞭な状態です。 |
| BCS3 | 理想体型 | 過剰な脂肪の沈着がなく助骨を触れます。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれが見られ、横から見た際は腹部の釣り上がりも見られます。 |
| BCS4 | やや肥満 | 脂肪の沈着はやや多いものの、肋骨は触れます。上から見て腰のくびれはありますが顕著ではなく、腹部の釣り上がりはやや見られる程度の状態です。 |
| BCS5 | 肥満 | 助骨は厚い脂肪に覆われて容易に触れません。腰椎や尾根部にも脂肪が沈着しています。腰のくびれはないか、ほとんど見られません。横から見て腹部の吊り上がりはないか、むしろ垂れ下がっている状態です。 |
年齢別の見分け方
ボディコンディションスコアは成犬を基準にしていますので、年齢によって少し見方を変える必要があります。子犬(パピー)の場合
幼犬は成長期ですから、栄養をたくさん摂る必要があります。しかし、肥満よりも栄養不足で痩せている子を見ることが少なくありません。その原因の一つとして、ペットショップなどで最初に教えてもらった量や与え方を変えずに続けていることが挙げられます。与えるごはんの量は、その子の成長に合わせて変えていかなければいけません。幼犬の頃は体重もどんどん変わります。1週間に1回は体重測定をして、その時その時で適切な量のごはんを食べさせるようにしましょう。
※1日の最適カロリー量は、ペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単に計算することができます。
シニア犬(老犬)の場合
シニア犬(老犬)は加齢によって正常な変化として体重が減少します。BCS3が理想であることに変わりはありませんが、少し痩せ気味だとしても許容範囲と考えて問題ないでしょう。ただし、急激に体重が増えたり減ったりする場合は病気の可能性がありますので、様子見をせずに病院に行くようにしてください。
犬が肥満の場合のダイエット方法(食事編)

健康なのに体重が増える理由は「食事量が多い」「運動量が少ない」のどちらか、もしくは両方です。また、チワワやトイプードルなど犬種によってダイエット方法が変わるわけではありません。まずは食事の見直しでできるダイエット法から解説していきます。
01【犬のダイエット方法】適量のフードを与える

エネルギーとして出ていく量より食べる量のほうが多ければ体重は増えていきます。飼い主さんで多いのは、「袋からごはん皿にザザーっとテキトーに入れている」パターンです。これで太っているなら食事量が適切ではありませんから、きちんと量って与えるようにしましょう。
次に多いのは、「ドッグフードのパッケージに書いてある体重あたりの推奨量を与えている」パターンです。「言われた通りに与えるのがダメなの!?」と思うかもしれませんが、私たちと同じく痩せやすい・太りやすい体質もあれば、同じ体重でも運動量が多い犬と少ない犬や不妊去勢手術の有無などで食事量は異なります。平均値としての推奨量ですので、愛犬に合った量を与えるようにしましょう。そのためには、1ヶ月に1度は体重を測り、増減を確認し、増えていてBCSも理想体型より増えたらカロリーを減らす、減っていてBCSも理想体型から減ったらカロリーを増やすようにしましょう。
もしかしたら、「平均値からズレていると言ってもちょっとした差でしょ?」と思うかもしれませんが、私たちと犬では体重が10倍以上の差があるわけですから、単純計算で犬にとっての10gは私たちにとっての100gになります。ダイエットをしている人が毎日ご飯を大盛りにしていたら痩せませんよね。

愛犬にとってのフードの適正量を知るために、毎日の与えるカロリー量を計算しましょう。毎日の最適必要量はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単に計算することができます。
愛犬のカロリー計算をする
02【犬のダイエット方法】おやつを与えすぎない

ごはんが適量だったとしても、おやつを食べすぎて摂取カロリー量オーバーになっている場合もあります。ごはんへのトッピングを含めて、おやつは1日の最適カロリー量の10%以内にしてください。
意識していただきたいのは、「家族全員でルールを守る」ということです。「お腹を空かせてかわいそう」とこっそりおやつを与えたり、食卓からわざとごはんを落としたり、犬のダイエットを阻む家族が隠れているかもしれません。全員が肥満のリスクを理解して取り組まなければいけません。
03【犬のダイエット方法】食物繊維でかさ増しダイエット

食べることが大好きな愛犬のごはんを減らすのはかわいそうと思う飼い主さんも多いと思いますが、食事量を減らさずにカロリー量を減らす方法として、食物繊維を使ったかさ増しがあります。食材としては野菜や「おから」がよく知られているのではないでしょうか。
食物繊維は「水に溶けやすい水溶性」と「水に溶けにくい不溶性」の2種類の特性を持ちます。水溶性は水に溶けてゲル状になって胃腸に溜まり、不溶性は保水してフードや糞便をかさ増しするのが特徴です。満腹感を得るためには水溶性、便秘がちな子には不溶性がいいでしょう。食物繊維は腸内細菌のエサになり腸内環境の改善にもつながります。
食物繊維を含む野菜などの食材としては以下がオススメです。最適カロリー量の10%以内を目安に、トッピングやおやつとして与えてください。食物繊維について解説した関連記事も参考にしていただくといいでしょう。
 |
 |
 |
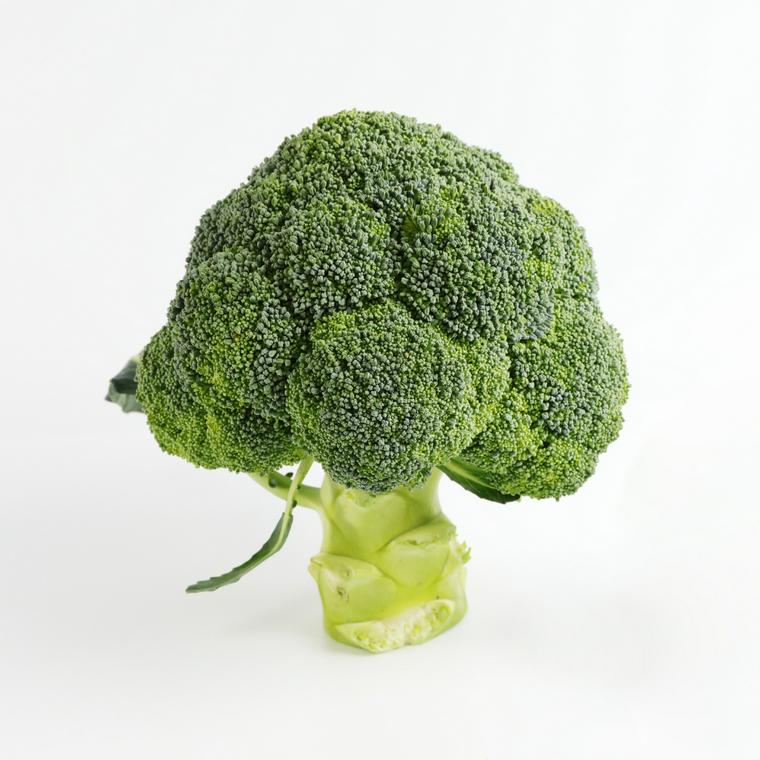 |
 |
 |
 |
 |
04【犬のダイエット方法】食事回数を増やす

多くの飼い主さんは愛犬の食事を1日2回にしていると思います。これは犬の消化スピードに合わせた回数ですが、与える量を変えずに回数を増やすことはダイエットに有効です。一気食いをしてしまう犬は特に「食事」という行為そのものに満足感を得る場合がありますので、1日3〜4回にわけてあげることを試してみてください。
05【犬のダイエット方法】食事を見直す

ドッグフードを見直すことも大切です。新鮮な食材を使用し、食材の栄養素を残し、消化に良いご飯を与えることが健康的な体重に近づける一歩です。ダイエットフードもありますが、あくまで低脂質フードになりますので、基本的には栄養バランスの取れた総合栄養食のごはんを与えるべきです。ペトコト代表・大久保の愛犬コルクもコーギーですが、ずっとスリムな状態をキープしています。
犬が肥満の場合のダイエット方法(運動編)

太っている理由で食事の問題にされがちですが、実は運動面に課題がある場合が多いです。私たちと同じく、1日に必要な摂取量と消費量で摂取量が大きく上回ると太っていきます。両面から見直すことで、ダイエットが成功しやすくなります。
06【犬のダイエット方法】定期的な散歩

ダックスフンド、ポメラニアン、ゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバー、ビーグル、パグなどは食欲旺盛で太りやすい犬種です。狩猟犬や牧羊犬など、犬種の特性として運動量が必要な犬種も見合った運動ができていないと太りがちです。ハウンド種やレトリーバー種、テリア種、日本犬などが当てはまります。
サイズでは大型犬より小型犬のほうが食事量の誤差が大きく影響するため太りがちです。小型犬の飼い主さんの中には室内運動だけで十分と考えている方もいるのですが、体力的に問題ない限り散歩がいらない犬はいません。外での散歩はストレス解消にもつながる重要なイベントですので、必ず家の外に出て適度な運動をするようにしてください。
07【犬のダイエット方法】プールなどで運動

関節に不安のある子やシニア犬(老犬)はなかなか運動量を確保するのが難しいと思います。最近はリハビリ用の犬用プールを備えた施設もありますし、お出かけができる子であればドッグランや宿泊施設の犬用プールを利用するのもいいでしょう。毎日とは言わずとも、定期的な運動をすることが大切です。
まとめ

肥満は確実に寿命を縮める
原因が病気か飼い方かを確かめる
ダイエットの基本は、適切な食事と運動
私たち人間の話ではありますが、犬も同様です。肥満は、恐ろしい病気へと続く最初のドミノと言えます。「ふっくらして可愛い」と油断するのではなく、愛犬の将来を考えて飼い主さんがしっかり対処してあげてください。
犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。
1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。
2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。
3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。
